コロナウイルス感染後に多くの方が悩まされる嗅覚障害。「あのレストランの料理の香りが楽しめない」「大好きな香水の香りがわからない」などの症状に悩まされていませんか?本記事では、嗅覚障害の症状と原因を解説するとともに、ツボ押しによる改善方法、嗅覚トレーニング、そして回復を促進する食事についてご紹介します。自宅で簡単にできるケア方法で、失われた嗅覚を取り戻す第一歩を踏み出しましょう。
コロナ後遺症の嗅覚障害とは?
コロナ後遺症の嗅覚障害は、感染から回復した後も続く厄介な症状の一つです。単に「匂いがわからない」だけでなく、様々な形で日常生活に影響を与えます。嗅覚は私たちの生活の質に深く関わっており、食事の楽しみが半減するだけでなく、ガス漏れなどの危険察知にも影響するため、早めの対処が望まれます。東洋医学の知恵を活用した「ツボ押し」は、西洋医学的な治療と並行して取り入れることで、回復を後押しする可能性があります。
嗅覚障害の症状:においがわからない、においが歪んで感じる
嗅覚障害には主に2つのタイプがあります。一つは「嗅覚脱失(きゅうかくだっしつ)」と呼ばれる、匂いを全く感じなくなる状態です。もう一つは「嗅覚錯誤(きゅうかくさくご)」と呼ばれる、匂いが歪んで感じられる状態です。
例えば、コーヒーの香りが腐ったにおいに感じたり、バラの香りが金属的なにおいに感じたりすることがあります。特に嗅覚錯誤は精神的な苦痛を伴うことも多く、食事の際に不快な匂いを感じてしまい、食欲不振につながるケースもあります。
このような症状は、多くの場合、感染から2〜3週間程度で自然に回復するといわれていますが、中には数ヶ月、あるいは1年以上続く方もいらっしゃいます。なぜ人によって回復期間に差があるのかは、まだ研究段階ですが、個人の免疫状態や神経の回復力などが関係していると考えられています。
嗅覚障害の原因:ウイルスによる嗅覚神経へのダメージ
コロナウイルスによる嗅覚障害の主な原因は、2つあります。
・ウイルスが鼻腔内の「嗅上皮(きゅうじょうひ)」と呼ばれる組織にダメージを与える
コロナウイルスは嗅上皮の「支持細胞」と呼ばれる細胞に感染します。この細胞は嗅覚受容体を直接持つ細胞ではありませんが、嗅覚神経を支える重要な役割を果たしています。支持細胞が損傷を受けると、嗅覚神経全体の機能が低下してしまうのです。
・炎症反応により鼻腔内の粘膜が腫れる
腫れることで、においの分子が嗅覚受容体にたどり着きにくくなるためです。
このようなメカニズムから、コロナウイルス感染後の嗅覚障害は、神経が直接破壊されるよりも、嗅覚システムの一時的な機能不全による場合が多いとされています。そのため、適切なケアと時間の経過によって回復が期待できるのです。
嗅覚障害に効果的なツボ3選
嗅覚障害の改善には、東洋医学に基づくツボ押しが効果的な補助療法となる可能性があります。特に嗅覚に関連するツボを刺激することで、鼻腔の血流が改善され、神経の回復を促進することが期待できます。ツボ押しは自宅で手軽に実践できるため、日常のケアとして取り入れる価値があるでしょう。以下では、特に嗅覚障害に効果的とされる3つのツボについて詳しく解説します。
迎香(げいこう):鼻の横にあるツボ。鼻づまり、嗅覚障害に効果的
迎香(げいこう)
・鼻の両脇、鼻翼の外側のくぼみに位置
・鼻づまりや嗅覚障害だけでなく、アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎の症状緩和にも効果的
効果的な押し方
①両手の人差し指の腹を使って、鼻の両脇にある小さなくぼみを見つける
②軽く押し当て、時計回りに20回程度、優しく円を描くようにマッサージします
※力加減は「気持ちいい」と感じる程度が適切です。強く押しすぎると粘膜を傷つける恐れがあるので注意しましょう。
このマッサージを1日3回(朝・昼・晩)行うことで、鼻腔内の血流が促進され、嗅覚神経の働きを活性化させる効果が期待できます。特に朝起きた直後と入浴後は、身体が温まっている状態なので、より効果を感じやすいでしょう。
上迎香(じょうげいこう):迎香の少し上にあるツボ。嗅覚を刺激
上迎香(じょうげいこう)
・鼻の付け根と目頭を結ぶラインの中間あたりに位置
・鼻腔内の神経に直接働きかけ、嗅覚の感度を高めると言われる
・特に「においはうっすら感じるけれど、はっきりしない」という方には効果的
効果的な押し方
①両手の親指または人差し指の腹を使って、眉毛の内側から鼻に向かって下りてきたところにある小さなくぼみを見つける
②そこを優しく押し当て、5秒間保持した後、5秒間リラックスするというリズムで、合計3分間ほど続ける
日常のケアとして、テレビを見ながらなど、リラックスした状態で行うのがおすすめです。
廉泉(れんせん):喉仏の上にあるツボ。嗅覚神経の働きを活性化
廉泉(れんせん)
・首の前面、喉仏のすぐ上のくぼみに位置
・のどや鼻の粘膜の状態が改善され、間接的に嗅覚機能の回復を促進
・唾液の分泌も促進されるため、口腔内の健康維持にも役立つ
効果的な押し方
①親指以外の4本の指を首の後ろに回し、親指で喉仏のすぐ上のくぼみを探す
②軽く押し込みながら、上下に小さく動かすようにマッサージをする
※なお、喉の部分にあるツボなので、押す際は力加減に十分注意し、決して強く押さないようにしましょう。不快感がある場合はすぐに中止してください。妊娠中の方は、このツボの刺激は避けた方が良いとされています。
1回につき30秒程度、1日2〜3回行うのが理想的です。
嗅覚トレーニングで嗅覚を回復
嗅覚障害の改善には、ツボ押しと並行して「嗅覚トレーニング」を行うことが効果的です。このトレーニングは、神経可塑性(脳や神経系が新しい経験に応じて再編成される能力)の原理に基づいており、欧米では既に医療現場でも広く活用されています。定期的にさまざまな香りを意識的に嗅ぐことで、損傷した嗅覚神経の回復を促進する効果が期待できるのです。
嗅覚トレーニングの方法:アロマオイル、コーヒー、レモンなど、香りの強いものを嗅ぐ
嗅覚トレーニングの基本的な方法は、特徴的な香りを持つものを意識的に嗅ぐことです。専門家が推奨する香りには、以下のような種類があります:
- 柑橘系:レモン、オレンジ、グレープフルーツなど(フレッシュな果物そのものか、精油)
- 芳香系:ローズ、ラベンダー、ユーカリなどの精油
- スパイス系:クローブ、シナモン、ペパーミントなど
- 樹木系:スギ、ヒノキ、サンダルウッドなどの精油
トレーニング方法
香りのするものを鼻に近づけ、10〜20秒かけてゆっくりと深呼吸
このとき、目を閉じて香りに集中し、その香りを言葉で表現してみるのも効果的です。例えば、「レモンの香りは明るく、さわやかで、少し酸っぱさを感じる」というように、連想されるイメージも一緒に思い浮かべるようにします。
おすすめアイテム
・アロマセラピーで使用される精油(エッセンシャルオイル)
市販のアロマオイルセットを活用すると、多様な香りで効率的にトレーニングできます。価格は2,000円〜5,000円程度のものが一般的で、ドラッグストアや専門店、オンラインショップで購入できます。
また、家庭にあるものでも代用可能です。コーヒー豆、紅茶の葉、スパイス類(シナモン、クローブなど)、柑橘類の皮、ミントの葉、石鹸なども有効な訓練材料となります。
トレーニングの頻度と期間:毎日数回、数週間〜数ヶ月
嗅覚トレーニングで効果を得るためには、継続的かつ規則的に行うことが重要です。研究によると、以下のようなスケジュールが推奨されています:
- 頻度:1日2回(朝と夜)、各香り10〜20秒ずつ
- 期間:最低3ヶ月間、理想的には6ヶ月間
- 方法:4種類の異なるタイプの香りを使用
効果実感のためには?
・嗅覚神経の再生には時間がかかるため、すぐに効果が現れなくても焦らず続ける
・トレーニングの進捗を記録する
例えば、「香りの強さを0〜10のスケールで評価する」「感じた香りの特徴をノートに書き留める」などの方法で、少しずつの変化を捉えることができます。市販の「嗅覚トレーニング記録ノート」も1,500円程度で購入可能です。
嗅覚障害に良い食べ物と栄養素
嗅覚障害からの回復をサポートするためには、適切な栄養素を十分に摂取することが重要です。特定の栄養素は嗅覚神経細胞の再生や修復を助け、回復プロセスを促進します。日常の食事に以下の栄養素を意識的に取り入れることで、ツボ押しや嗅覚トレーニングの効果をさらに高めることができるでしょう。
亜鉛:嗅覚細胞の再生を助ける
亜鉛は嗅覚機能において特に重要な栄養素です。亜鉛は新しい細胞の生成に必要なDNAやタンパク質の合成に関わり、嗅覚細胞の再生と修復を促進します。実際、亜鉛欠乏症の症状の一つとして嗅覚障害が知られています。
亜鉛を豊富に含む食品としては、以下のようなものがあります:
- 牡蠣:100gあたり約14mgの亜鉛を含み、最も豊富な食品源です
- 牛肉:100gあたり約5mgの亜鉛を含みます
- 豚レバー:100gあたり約6mgの亜鉛を含みます
- 大豆製品:納豆(100gあたり約3mg)や豆腐(100gあたり約1mg)
- かぼちゃの種:30gあたり約2.5mgの亜鉛を含みます
日常的に摂取するには
・週に1〜2回、牡蠣料理を食事に取り入れる
・牛肉や豚肉を使った料理を増やす
ことがおススメです。特に牡蠣は多く亜鉛を含むため効率的に摂取することができます。牡蠣フライ、牡蠣の土手鍋、牡蠣グラタンなど、様々な調理法で楽しんでみてください。
なお、成人の亜鉛の推奨摂取量牡蠣は1日あたり男性10mg、女性8mg程度です。過剰摂取は銅の吸収を阻害するなどの副作用がありますので、サプリメントを利用する場合は医師に相談することをおすすめします。
ビタミンA:嗅覚粘膜の健康維持
ビタミンAは、鼻腔内の粘膜を含む上皮組織の健康維持に欠かせない栄養素です。粘膜が健康であることは、においの分子が嗅覚受容体に到達するために重要です。また、ビタミンAは免疫機能の維持にも役立ち、鼻腔内の炎症を軽減する効果も期待できます。
ビタミンAを豊富に含む食品には、以下のようなものがあります:
- レバー類:牛レバー(100gあたり約13,000μgのレチノール)
- 緑黄色野菜:ニンジン、ほうれん草、かぼちゃなど(β-カロテンの形で含まれます)
- 乳製品:バター、チーズ(特にゴーダチーズなど)
- 魚介類:うなぎ、サーモン、イワシなど
日常的に摂取するには
・毎日の食事に人参や小松菜などの緑黄色野菜を取り入れる
β-カロテン(体内でビタミンAに変換される)を効率的に摂取できます。人参なら1本(約200g)で1日に必要なビタミンA量を十分に摂取できます。
・週に1回程度、レバニラ炒めなどのレバー料理を食べる
直接的にビタミンAを補給することができます。レバーは非常に栄養価が高く、亜鉛も豊富に含まれているため、嗅覚障害の回復に特におすすめです。
なお、ビタミンAは脂溶性ビタミンであるため、油と一緒に調理すると吸収率が高まります。例えば、人参のグラッセやかぼちゃの煮物など、少量の油を使った料理がおすすめです。
まとめ:嗅覚障害はツボ押しと嗅覚トレーニングで改善を目指そう
コロナ後遺症としての嗅覚障害は、日常生活に大きな影響を与える厄介な症状ですが、適切なケアと時間の経過によって改善が期待できます。本記事でご紹介した方法を総合的に取り入れることで、回復の可能性を高めることができるでしょう。
嗅覚の回復には個人差があり、すぐに効果が現れない場合もありますが、諦めずに継続することが重要です。香りを感じる喜びを取り戻すための第一歩として、今日からできることから始めてみませんか?


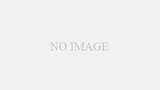

コメント